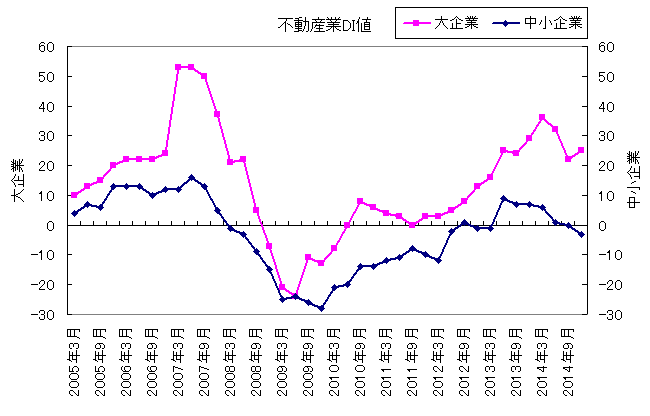○鑑定コラム
フレーム表示されていない場合はこちらへ
トップページ
田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ
前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ
日本銀行が景気動向を調べる為に、各産業の会社に対して、売上高等景気の良し悪しについてアンケート調査を、四半期毎に行っている。
この日銀の四半期毎の景気判断の調査は、「短観」として発表されている。
短観の正式名称は、「全国企業短期経済観測調査」である。
その調査数値は、「DI値」で発表されている。
DI値とは、Diffusion Index(ディフュージョン・インデックス)の略である。
業況判断数値である。「業況判断DI値」と呼ばれ、あるいは「短観DI値」呼ばれている。
業況が良い企業数から業況が悪い企業数を差し引き、それを回答企業数で割って、100を乗じた数値がDI値である。
業況が横ばいの企業数は計算に含まれない。
この日銀の発表DI値は、日本の経済、景気の判断に大きな影響を与えている。
その日銀短観のDI値調査の中には、不動産業も含まれている。
大手不動産業、中堅不動産業、中小不動産業の3つの規模の調査が行われている。
不動産業DI値分析は、不動産価格動向、不動産業の業況を知るためには重要な分析手法であると私は思い、私が日銀のDI値を利用するようになったのは、昭和の50年代の後半頃では無かったかと思う。平成バブルの少し前であったと思う。
日銀の調査の不動産業3つの中で、中小不動産業のDI値が、土地価格の変動と良く合致すると知った。割と実態に近い数値であると当時実感した。
それ以後、この数値を把握して不動産の景気動向を判断し、不動産鑑定にも利用していた。
業況が良い多い DI値はプラス = 土地価格が上昇している
業況が悪い多い DI値はマイナス = 土地価格は下落している
業況判断DI値と土地価格とは相関関係が強い。
右肩上がりで「0」の場合は、底値価格
右肩下がりで「0」の場合は、頂上価格
とほぼ判断出来る。
なお、その後、国交省の外郭研究団体である土地総合研究所も、DI値を発表するようになった。
2005年からの日銀の不動産業の大企業、中小企業の業況判断DI値のグラフを示すと、下記である。
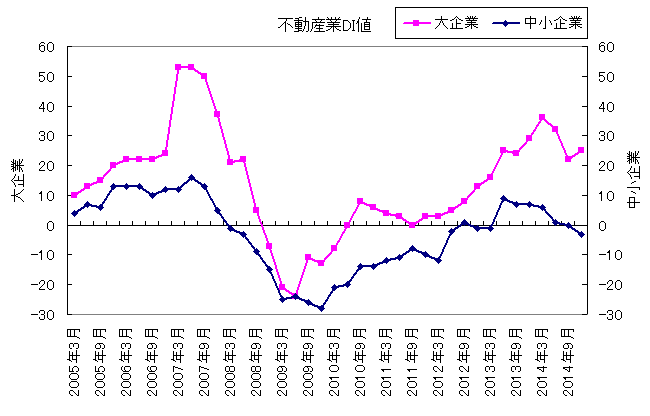
2007年の山は、不動産ファンドバブルの山である。
2014年の山は、現在のリートバブルの山である。
最近の不動産業の大企業、中小企業の業況判断DI値は、下記である。
大企業 中小企業
2013年6月 25 9
2013年9月 24 7
2013年12月 29 7
2014年3月 36 6
2014年6月 32 1
2014年9月 22 0
2014年12月 25 -3
2014年9月と12月のDI値を見ると、大企業は22→25とアップしている。
これに比し、中小企業のDI値は、0→-3とゼロを切っている。
同じ不動産業の中で、大きい業者と小さい業者で業況の向きが真反対になっている。
この現象はどうしたことか。
大企業は、銀行からの資金が豊富で、リートや分譲マンションで景気は良い。
中小企業は、資金は豊富で無く、リートや分譲マンションの景気の蚊帳の外にあると云うことを示しているのであろうか。
中小企業の不動産業者のDI値が、不動産業の実態を良く反映しており、そのDI値は土地価格の動向にも良く合致していると判断出来ることから、その中小企業のDI値がゼロを切ってマイナスになったということは、現在のリートバブルは峠を越したと判断される。
(2015年1月23日の田原塾1月会の講話テキストに追加して)
鑑定コラム507)「不動産業の業況の分水嶺は2007年7月だった」
鑑定コラム949)「不動産価格DI値は11不動産鑑定士会で発表している」
鑑定コラム1289)「不動産業の業況が少しおかしいぞ 5 住宅ローン貸出額」
鑑定コラム1275)「不動産業の業況が少しおかしいぞ」
鑑定コラム1312)「リートバブルは峠を越えた」
▲
フレーム表示されていない場合はこちらへ
トップページ
前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ